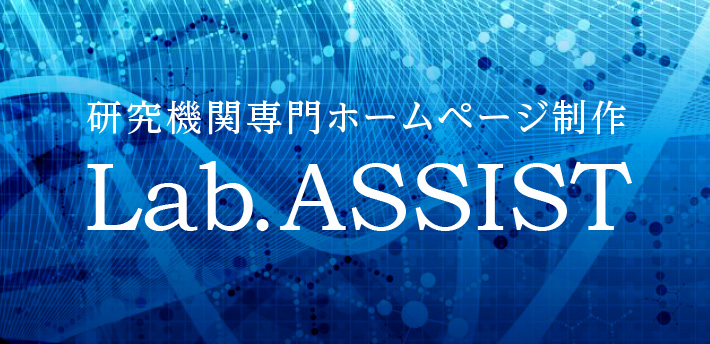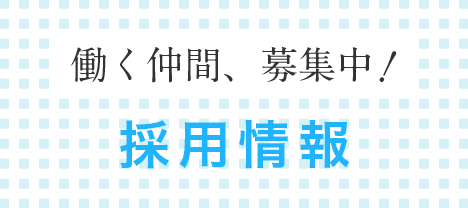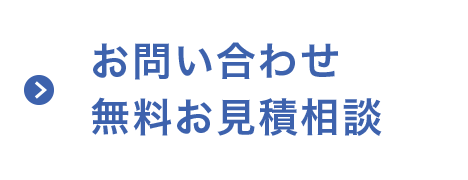先日、お客さまのサイトのアクセスレポートをチェックしていると、アクセス数が突出している日を見つけました。なんと普段の4~5倍の訪問者数です。
さっそく詳しく調べてみると、どうやらお客さまが書かれているブログの記事が、とある人気の「まとめサイト※」に取り上げられ、リンクを貼られたことで、アクセスが急増したようなのです。さっそくお客さまに報告し、内容の確認をしていただくようお伝えしました。
皆さまのホームページも、いつどこで「まとめサイト」に取り上げられるか分かりません。
今回の例のように、多くの方が訪れて宣伝の機会となれば良いですが、ひょっとすると古い情報が一人歩きして広まってしまう可能性もあり、やはり注意が必要です。
そういった状況を避けるためにも、定期的なホームページのチェックや見直しは欠かせません。毎月チェックしているお客さまのアクセスレポートに普段と違う動きがあれば、より深く調査することで、見落とされがちな情報も発見でき、問題の早期解決が期待できます。
そう、ホームページにも定期検診が必要なんですね。
※まとめサイト
情報を整理してまとめてくれるサービス(Webサイト)。人が集まりやすく広告収入も見込めるため、最近では「まとめサイト」の作成ツールや、「まとめサイトのまとめサイト」も登場しています。